FAQ(よくあるご質問)
マグロ解体ショーの価格について
鮪匠では、お客様のご予算やご要望に応じて、無駄のない各種プランをご用意させて頂いておりますので、 今まで高額だったマグロ解体ショーが、なんと10万円からの対応が可能になりました! なお、地域により別途交通運搬費等の費用がかりますのでその旨ご了承ください。
■マグロ種類別から選択(マグロ・人件費・各種オプション込み)
■マグロ品質別で選択(マグロ・人件費・各種オプション込み)
■交通運搬費等の目安
マグロ解体ショーに必要なスペースや開催時間について
マグロ解体ショーに必要なスペースにつきましては、幅2.5m×奥行2m×高さ3mほどのスペースがあれば開催は可能です。開催スペースに水回りが無くても対応可能です。
■イメージ写真
開催時間は、マグロの大きさやイベントの内容によって前後しますが、基本的な流れはショーの時間で約20分、その後、仕込み振る舞いまでの時間を合わせて1~2時間以内での対応となります。※開催場所への入り時間につきましては開始時間の90~120分前となります。開催時間含め時間調整は可能です。
■イメージ写真
開催時間は、マグロの大きさやイベントの内容によって前後しますが、基本的な流れはショーの時間で約20分、その後、仕込み振る舞いまでの時間を合わせて1~2時間以内での対応となります。※開催場所への入り時間につきましては開始時間の90~120分前となります。開催時間含め時間調整は可能です。
衛生管理(臭い汚れ等)について
衛生管理については細心の注意を払い、マグロは自社認定工場(QC認証)にて事前処理(除菌、血抜き、鰓腸除去、保冷)を行い、保健所からの食品営業許可並びに、魚介類販売業を取得した上で、一般社団法人全国鮪解体師協会(JADT)による衛生基準の下、現場での衛生管理を徹底し、ブルーシートでの養生、現場が汚れたり臭いが残るようなことがないようマグロ解体師認定者が対応させていただきますのでご安心ください。
■鮪匠施設情報
その他、オプション対応について
鮪匠ではお客様のご要望に応じて、開催場所の手配や飲み物、オードブル等のご注文も承っておりますのでお気軽にお申し付けください。
各種マグロの特徴について
マグロの種類は8種類あり、主にご提供するマグロは、クロマグロ(太平洋/大西洋)・ミナミマグロ・メバチ・キハダ・ビンナガの6種類のマグロになります。各種マグロの特徴については詳細を下記に記していますのでご参照ください。また、価格についてはビンナガに対し、キハダ、メバチで約1.3倍、ミナミマグロ、クロマグロで約2倍の価格とお考えください。
●クロマグロ(通称本マグロ)について
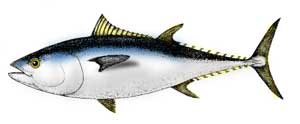
大西洋、地中海、日本近海で獲られ、肌が黒っぽい事からクロマグロと呼ばれています。また、別名シビ、ホンマグロとも呼ばれています。身質は硬くなく、酸味があり大型で、体長3m、体重400kg以上に達するものもあります。3kg~8kgのものをメジマグロ、20kg前後を大メジ、40kg前後は中鮪(チュウボウ)と呼び、大体50kg以上が成魚とされます。中でも80kg~150kg前後のものはスジも薄く大変に美味で、寿司や刺身にすると最適です。 腹の霜降り部分が「大トロ」、背の皮ぎし部分が「中トロ」で、口の中でとろける味わいは格別である。 クロマグロは近海物が上物で、特に冬期の北海道沖で獲れるものが最高級品。
●ミナミマグロ(通称インドマグロ)について
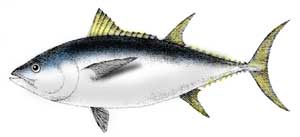
オーストラリア、ニュージーランド、ミナミアフリカ(ケープタウン)沖の低水温の海域で獲られています。脂が乗っていることから高級まぐろとして寿司屋、料亭でよく使われています。また、別名インドまぐろとも呼ばれていて、南半球に生息する事からそう呼ばれています。身質は硬めで、少し酸味があり、体長2m、体重200kgのものもあります。その初めは南インド洋から帰港した漁船が運んできたものであり、初めはインド洋の赤道近くの熱帯のものが中心でしたが、最近は冷凍技術の進歩により赤道を越して寒い南へと漁場を開拓し、南緯40度前後のケープタウン、タスマニア、ニュージーランドなど広い地域から入荷するようになり、入荷量のほとんどが冷凍物になりますが、現在ではオーストラリア産の生の養殖インドマグロも多く空輸されています。ミナミマグロは酢めしと相性がよく、甘みのある食感はクロマグロと人気を二分するほどです。
●メバチ(メバチマグロ)について
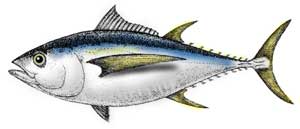 赤道をはさんで南北の緯度約35度にわたる広い範囲で獲られます。漁獲量の一番多いまぐろで目玉が大きくぱっちりしていて目が鉢のように丸いことから通称目鉢マグロと呼ばれています。身質は柔らかめで、甘味があり、体長2m、体重150kg以上に成長します。小さいものでは、20kg以下をダルマ、40kg以下を中バチと呼び、関東から東北地方にかけて寿司種や刺身用として人気があります。 クロマグロと比べ腹身はやや薄く、寿司種にすると酢めしに良く馴染むので喜ばれています。近年は近海物の他、太平洋、大西洋、インド洋、地中海で広く漁獲されますが、そのほとんどはチリ沖、ペルー沖、北米方面などから来る冷凍物で、それにインドネシアを中心にオーストラリアやニューヨーク沖などからの空輸の生が加わります。
赤道をはさんで南北の緯度約35度にわたる広い範囲で獲られます。漁獲量の一番多いまぐろで目玉が大きくぱっちりしていて目が鉢のように丸いことから通称目鉢マグロと呼ばれています。身質は柔らかめで、甘味があり、体長2m、体重150kg以上に成長します。小さいものでは、20kg以下をダルマ、40kg以下を中バチと呼び、関東から東北地方にかけて寿司種や刺身用として人気があります。 クロマグロと比べ腹身はやや薄く、寿司種にすると酢めしに良く馴染むので喜ばれています。近年は近海物の他、太平洋、大西洋、インド洋、地中海で広く漁獲されますが、そのほとんどはチリ沖、ペルー沖、北米方面などから来る冷凍物で、それにインドネシアを中心にオーストラリアやニューヨーク沖などからの空輸の生が加わります。
●キハダ(キハダマグロ)について
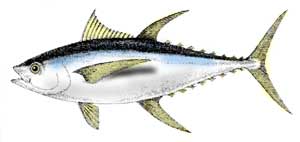
メバチとほぼ同じ漁場で獲られ、肌が黄色いことから通称黄肌マグロと呼ばれています。体型がスマートなのが特徴で、赤身のあっさりした味わいが楽しめます。身質は硬めで、酸味があり大きなキハダは体長2m、体重100kg以上になります。小さいものは、20kg以下をキメジ、20kgから40kgくらいを小キハダと呼び、肉色は全体に桃色で、他のマグロと比べると赤身とトロの区別がありません。 名古屋以西の関西方面の需要が多く、酢めしにあまり馴染まないので、寿司種よりむしろ刺身用に好まれています。 晩春から初夏にかけてが旬で、特に近海で獲れるキハダの味は絶品であり、クロマグロに勝とも劣らないといわれています。 こうした脂がのった近海物は寿司にも合い、高級割烹料理店などでも好まれています。
●ビンナガ(通称トンボ)について
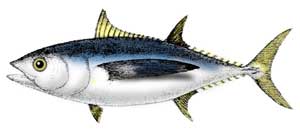
世界中の海に広く分布し、北太平洋を東西に渡り大回遊することで知られている小型のマグロです。長い刀状の胸びれが特徴で、胸ビレが長いので、袖長(ビンチョウ)とも呼ばれ、トンボが飛んでいる姿に似ていることからトンボマグロとも呼ばれています。マグロ類中最も小型の魚で体長は1m前後、体重40kgほど、肉質が柔らかく、主にシーチキンの材料などに使用されますが、脂ののったビントロなどはすしネタや刺身としても人気があります。
鮪匠(まぐろのたくみ)とは?
鮪匠は2001年3月創業、マグロ流通に関わる有識者メンバーによる第三者機関、一般社団法人全国鮪解体師協会(JADT)が直轄管理しているマグロ解体ショー専門のプロフェッショナル集団です。 全国に張り巡らされたマグロ産地、消費地における市場関係者、生産者とのダイレクトな仕入ネットワークの下、厳選したマグロを品質に応じた適正な価格で流通させることを使命とし、マグロ解体師資格取得者による品質認証されたマグロを取り扱うことにより、日本で唯一、JADTより公認されたマグロ解体ショーを行っております。
■公認マグロ解体ショーとは
■マグロ単価表/品質評価基準
個人情報の取扱いについて
お客様の個人情報を安全に送受信するため、鮪匠WEBサイトURL(httpsで始まる)ページにおいて、WEBサーバーとブラウザ間の通信は暗号化されています。また、その安全性、信頼性の保証、維持、改善を続けていくとともに個人情報保護への取り組みをより一層強化しております。なお、マグロ解体ショー開催の模様につきましては、サービス向上の一環も含め鮪匠WEBサイト内での新着情報、sns等でご紹介させていただいておりますが、お客様の企業名、個人情報等のプライバシーには十分に配慮させていただいておりますのでご安心ください。
■SSLサーバ証明書について








